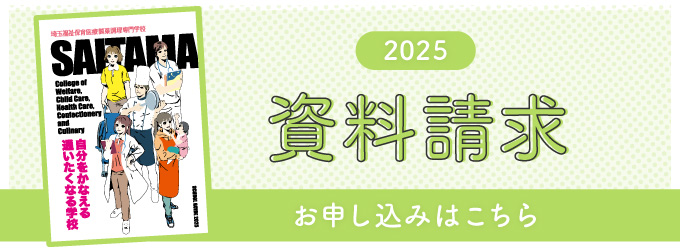言語聴覚士と他リハビリ系国家資格との違い

理学療法士と作業療法士と言語聴覚士の違い
ケガや病気で困っている人を、自分の手で直接支える仕事に就きたい。
そんな人にオススメなのが「リハビリテーション専門職」です。リハビリテーションと聞くと、ケガや事故などで身体が思うように動かせなくなってしまった患者さんが、機能回復をめざして行う訓練のことだとイメージすると思います。しかし、実はそれだけではありません。
加齢、障害が原因で、日常生活に不自由が生じてしまった人たちを、専門的な知識や技術で支えるリハビリテーション専門職もあります。
今回は、リハビリテーション専門職(以下、リハビリ職)の中から、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)の3つについて、それぞれの特徴を詳しくご紹介していきます。
INDEX
基本情報
このページで紹介する3つのリハビリ職に加えて、進路決定の際にリハビリ職と迷う方が多い看護師を比較してみましょう。
| 言語聴覚士 Speech-Language- Hearing Therapist(ST) |
理学療法士 Physical Therapist(PT) |
作業療法士 Occupational Therapist(OT) |
看護師 nurse(NS) |
|
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 音声や言語や聴覚の障害 | 身体の障害 | 身体または精神の障害 | 身体または精神の障害 |
| 目的 | ||||
| 国家試験合格率 (令和5年) |
67.4% | 87.4% | 83.8% | 90.8% |
| 資格者数 | 約3万人 | 約16万人 | 約9万人 | 約129万人 |
| 平均年収 | 430万6800円 | 430万6800円 | 430万6800円 | 508万1300円 |
| 開業できるのか | 開業可能 ※言語障害、言語訓練、構音訓練 ※嚥下訓練や補聴器装用訓練は除く |
開業不可 ※医師の指示が必要のため ※個人事業主としては可 |
開業不可 ※医師の指示が必要のため ※個人事業主としては可 |
開業可能 ※訪問看護ステーション・介護施設(デイサービス・グループホーム)・助産院 |
仕事について
どんな仕事?
-
-
言語聴覚士(ST)
-
-
-
理学療法士(PT)
-
作業療法士(OT)
言語聴覚士(ST)
言語聴覚士は「話す」「聞く」「食べる」などについて、日常生活に問題を抱える人に対してリハビリを行う職種です。
日本言語聴覚士協会では、英語表記を「Speech-Language-Hearing Therapist」としているため、日本国内では一般的に「ST」と略されます。
言語の発達に遅れがある子どもや、脳卒中の後遺症が原因の失語症など、「話す」「聞く」がうまくできない人たちや、病気や加齢による筋力の衰えが原因で、食べ物をうまく飲み込めなくなってしまった高齢者など、さまざまな年齢層や状態の方々を対象とします。
専門知識を用いて症状を見極め、適切なリハビリテーションを計画し、実践していく力が求められます。専門性の高い職業なので、現場から必要とされ、頼られているという強い実感を得られる仕事です。
理学療法士(PT)
「リハビリ職」の中でも、多くの人たちに認識されているのが理学療法士だと思います。理学療法士は、ケガや病気、加齢などで身体に問題を抱えた患者さんに対して、運動療法や物理療法を行う専門職です。
英語では「Physical Therapist」と呼ばれているため、「PT」と略することもあります。
運動療法では、歩行などの基本動作、関節の可動域および筋力を維持・改善する運動などを行います。物理療法では、電機や温熱機器などを用いて治療します。
作業療法士(OT)
作業療法士は、運動や感覚・知覚、精神・認知などの心身機能という「基本的動作能力」、食事や入浴、トイレなど、手を使った細やかな作業を行うための「応用的動作能力」、地域活動や就学・就職を実現するための「社会的適応能力」という、3つの能力の維持・改善をめざしたリハビリテーションを行う専門職です。
英語では「Occupational Therapist」と言われていて、「OT」と略されます。
脳卒中や脊髄損傷などが原因で身体が不自由になった人だけでなく、総合失調症や感情障害など、心に問題を抱えている人もサポートします。
患者さんの状態や生活様式のほか、ご自身やご家族がどのような暮らしを取り戻したいのかなど希望にもしっかりと向き合いながら、一人ひとりに適切なリハビリを行っていきます。
例えば、患者さんの状態や身体に合わせて、食事をするためのスプーンを作ってリハビリに励んだり、車いすなどの「福祉用具」の選定を行ったりします。
専門的な技術・知識をベースにしながら、創意工夫しサポートできるのが、作業療法士の大きな魅力です。
必要な資格&合格率は?
言語聴覚士(ST)
言語聴覚士になるには、国家資格を取得する必要があります。
受験資格を得るための条件は、高校卒業者と大学卒業者で異なります。
高校卒業者の場合は、文部科学大臣が指定する学校(大学や短期大学)もしくは都道府県知事が指定する言語聴覚士養成所(専門学校など)を卒業しなければいけません。
大学卒業者の場合は、指定された大学および大学院の専攻科、または専修学校(2年制)を卒業することで受験資格を得ることができます。
試験は、年に1回行われます。
平成5年に実施された「第25回言語聴覚士国家試験」の合格率は、67.4%。
2515名が受験し、1696人が合格しました。
理学療法士(PT)
理学療法士になるには、理学療法士国家試験に合格しなければいけません。
受験のためには、大学、短期大学、専門学校などの養成校で3年以上学び、必要な知識と技術を身につけることが必要です。
試験は年に1回実施されます。
令和5年に行われた「第58回理学療法士国家試験」の合格率は87.4%。
1万2948人が受験し、1万1312人が合格しました。
作業療法士(OT)
作業療法士国家試験に合格する必要があります。国家試験を受験するには、大学、短期大学、専門学校などの養成校で3年以上学び、必要な知識と技術を修得しなければいけません。
試験は年に1回実施されます。
令和5年に行われた「第58回作業療法士国家試験」の合格率は83.8%。
5719 人が受験し、4793人が合格しました。
活躍できる場所は?
言語聴覚士(ST)
病院や診療所などの医療機関のほか、介護老人保健施設、地域包括支援センター、障害者福祉施設、小児療養センター、特別支援学校など、さまざまな領域の現場で活躍することができます。
理学療法士(PT)
病院やクリニック、診療所、大学病院、訪問看護ステーションなどの医療施設のほか、特別養護老人ホーム、デイケアサービスセンターなどの高齢者を対象とした施設や、福祉施設などで働くことができます。さらに、行政施設や教育・関連施設、スポーツ関連施設などで活躍する理学療法士もいます。
作業療法士(OT)
病院やクリニックなどの医療機関、児童発達支援センターや障害福祉サービス事務所などの福祉機関のほか、介護老人保健施設、就業・生活支援センター、地域包括支援センター、特別支援学校など、幅広い分野の現場で活躍することができます。
どんな人が向いている?
-
-
言語聴覚士(ST)
-
-
-
理学療法士(PT)
-
作業療法士(OT)
言語聴覚士(ST)
リハビリ職は、基本的な医療の知識が必要になります。言語聴覚士にも「理系」のイメージを強く持たれる人が多いです。実際に解剖学的な知識は必要です。しかし、主に対象とする身体の部位は首から上となるため、覚える必要のある筋肉は30前後で、理学療法士と比べるとその数は三分の一程度になります。
言語聴覚士は、活躍する場によっては成人の言語治療や、小児の発達、心理、言葉に関する基礎知識も求められるため、「文系」の人でも得意科目をいかして活躍することができます。
国家試験の合格率は67%(2023年)となるため、「理系」でも「文系」でも、コツコツまじめに勉強する姿勢が必要になります。「人と話すのが苦手」という人でも、大丈夫。大切なのは、対象者にしっかり向き合う姿勢です。
理学療法士(PT)
理学療法士は歩行のリハビリも行います。その際には、身体全体を見るため、100を超える筋肉や骨格などの名称を覚える必要があります。身体の仕組みや、筋肉・骨格の機能などに興味を持っている人は、学びやすいかもしれません。
さらに、リハビリを行うだけでなく、医師や看護師と連携しながら患者さんの治療に挑みます。人との会話が好きな人や、明るく前向きな人に向いていると言えるでしょう。
また、患者さんのちょっとした動作などから状態を把握することも求められるため、観察力を持っていることが望ましいです。
作業療法士(OT)
一人の患者さんと、比較的長い期間を通して密に関わる仕事です。人との会話が好きな人、根気強い人に向いていると言えるでしょう。
また、患者さんの状態や生活様式、ご希望に合わせたリハビリを提案・実施しなければいけないので、柔軟な発想力や遊び心を存分にいかすこともできます。
年収は?
平成4年に行われた調査によると、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の平均年収は430万6800円です。(平均月収=30万700円、平均年間賞与額=69万8400円)
言語聴覚士科の詳細はコチラ!
 2023年4月 埼玉福祉保育医療専門学校より校名変更
2023年4月 埼玉福祉保育医療専門学校より校名変更